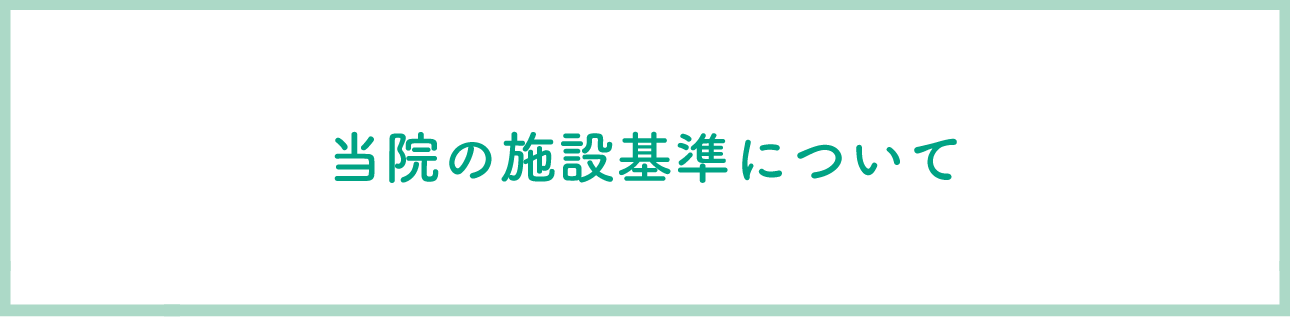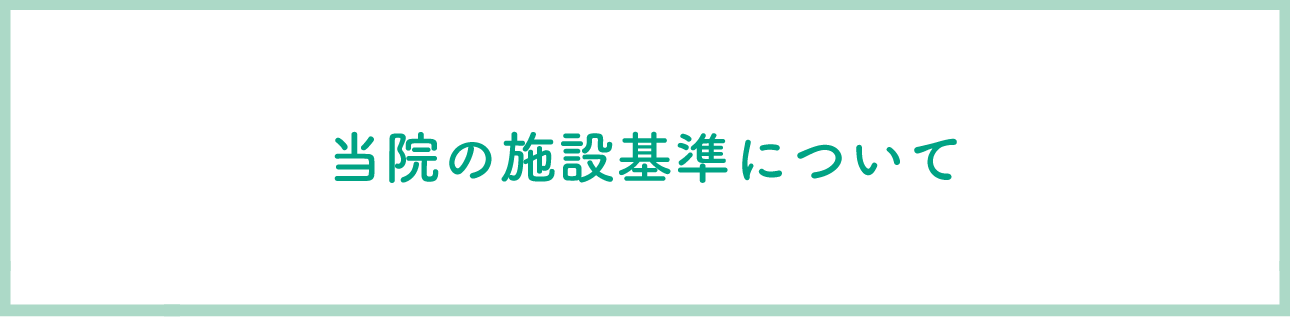
国民の信頼に応えるかかりつけ医として (日本医師会より抜粋)
「かかりつけ医」とは、患者さんが医師を表現する言葉です。「かかりつけ医」は患者さんの自由な意思によって選択されます。どの医師が「かかりつけ医」かは、患者さんによってさまざまです。
患者さんにもっともふさわしい医師が誰かを、数値化して測定することはできません。だからこそ、わたしたち医師は、心をこめてひとりひとりの患者さんに寄り添います。
そうして患者さんに信頼された医師が、「かかりつけ医」になるのです。患者さんと「かかりつけ医」の信頼関係にもとづいて、全国でさまざまな形のかかりつけ医機能が発揮されています。
わたしたち医師は、かかりつけ医機能をさらに深化させるとともに、より温かみのあるものにしていきます。

「かかりつけ医」の努め
わたしたち医師は、患者さんに信頼される「かかりつけ医」になるべく、これまで以上にかかりつけ医機能を発揮し、誠意をもって、患者さんを包括的かつ継続的に支えていきます。
- 患者さんに、いつでも、なんでも相談していただけるよう、しっかりとコミュニケーションをとって診察します。診察の結果をわかりやすい言葉で伝え、患者さんのライフスタイルを理解したうえで患者さんと治療目標を共有します。必要なときには、適切なタイミングで適切な専門の医師や医療機関につなぎます。そのために日頃から、地域の医師たちとの対話を深め、患者さんをチームとして支えます。
- いつでも安心していただけるよう、かかりつけ医を中心に地域の医師がチーム一丸となって患者さんを支えます。外来へのアクセスが困難な患者さんのために、在宅医療やオンライン診療など、患者さんのそばに寄り添える方法を選択します。
- 日々、新しい医療技術の研鑽を積み、患者さんおよびご家族とともに最善の治療を選択します。
- 患者さんの意思を尊重し、ご家族とともに、患者さんの尊厳ある生き方を支えます。
- 予防接種や健康診断を担い、生活のこと、仕事のことも含め幅広く患者さんおよびご家族からの健康相談を受け、必要なときに適切な医療につなげます。
- 患者さんの主治医意見書の作成をはじめ、患者さんの希望を受け止めて、地域の介護サービスや福祉サービスにつなぐなど、地域包括ケアシステムの中で求められる役割を果たします。
- 患者さんがもっとも安心・安全かつ効率的に最善の医療に到達できるよう医療のデジタル化を進めます。患者さん個人を守ることを絶対の条件として、また、地域の方々がより効果的に予防・健康づくりを進められるよう、医療情報を活用します。

地域社会におけるかかりつけ医機能
わたしたち医師はお互いに協力し、さまざまな職種の方とも協力して、医師それぞれの特性を活かして地域住民の健康を支えます。主に医師会活動として行っています。
- 健康相談、予防接種、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健などの社会的な活動や、警察医などの行政活動に協力します。
- 災害が起きた地域の医療支援活動に参加し、被災者の方の健康管理や診療などを担います。
- 24時間365日、安心して相談、受診していただけるよう地域の医師同士で連携する体制をとるとともに、在宅当番医や休日夜間急患センターの業務を分担します。
参考サイトは
こちらから

当院では以下の各項目の診療報酬施設基準を整備したうえで関東厚生局に届出をして、算定をしています。
【基本診療料】
夜間・早朝加算
機能強化加算
外来感染対策向上加算
連携強化加算
医療情報取得加算
時間外対応加算1
明細書発行体制等加算
一般名処方加算
【特掲診療料】
特定疾患療養管理料
小児科外来診療料
小児かかりつけ診療料
小児抗菌薬適正使用支援加算
乳幼児育児栄養指導料
生活習慣病管理料
医療DX推進体制整備加算
外来・在宅ベースアップ評価料
☆当院はマイナンバーカードによる
オンライン資格確認に対応しています
受診された患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他、必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。
☆当院では医療DX推進の体制に関する事項
及び質の高い診療を実施するための
十分な情報を取得及び活用して診療を
行っております。
マイナ保険証の活用により、医療DXが進んでいます。患者様の薬剤情報、特定健診情報、他医療機関の受診状況などから、総合的な医療提供が可能になります。
また、2024年6月より電子処方箋発行開始予定、メーカーの準備が整い次第、電子カルテ共有サービスも導入予定です。
さらに、独自のDX化としてYouTubeによる疾患別の説明を動画配信することにより、患者様により理解を深めてもらえるよう努力しております。
☆当院は患者様の状態に応じ、
28日以上の長期投与又は
リフィル処方箋の交付に対応可能です。
詳しくはこちら
☆感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律
当院は令和6(2024)年4月1日施行の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第36条の3第1項の規定に基づき栃木県(以下「県」という。)と病院及び診療所(以下「医療機関」という。)との医療措置協定(以下「協定」という。)の締結をし、並びに法第38条第2項の規定に基づく医療機関への第二種協定指定医療機関(以下「協定指定医療機関」という。)の指定を受けています。

小児かかりつけ診療料
- 急な病気の際の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。
- 発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じるとともに、専門機関への紹介を行います。
- 不適切な養育にもつながりうる育児不安等の相談に適切に対応したします。
- 予防接種の状況を確認し、接種の時期についてのスケジュールや指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
- オンライン資格確認等のDXを利用し、必要に応じて、専門医、専門医療機関に紹介します。
- 「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等によるお問い合わせに原則常時対応しています。
【基本診療料】
お電話がつながらない際は一旦、小児救急医療相談「#8000」にご連絡ください。
小児かかりつけ診療料に登録できる方:よこやま内科小児科クリニックを継続して受診されている6歳未満のお子さんが対象です。
※登録には「小児かかりつけ診療料」に関する同意書に署名が必要です。当クリニックで「小児かかりつけ診療料」の登録をご希望の方は受付にてお申し出ください。

一般名処方加算について
厚生労働省は医療費の削減のために後発医薬品の使用促進を推奨指導しています。当院ではその指導に基づき後発医薬品使用と安定供給に向けた取り組みをなどを実施しています。
一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載すること
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っております。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
一般名処方加算1 10点
(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
一般名処方加算2 8点
(後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)
また、2024年10月の改定により、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養という制度が導入されました。
患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく制度です。
詳しくは
こちら

マイナンバーについて
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
お手元の健康保険証の有効期限・マイナ保険証の使い方など、詳しくは下記から確認できます。
健康保険証・マイナ保険証について
詳しくはこちら
医療機関・薬局での受付について
詳しくはこちら
保険診療の自己負担額について
詳しくはこちら
マイナ保険証の利用つきまして、スタッフが丁寧にご案内しております。まだ、マイナンバーカードと保険証の連携ができていない方でも、当院窓口にある端末にて、連携が可能です。クリニックご受診の際はマイナンバーカードをお持ちください(マイナンバーカードの取得については
こちらをご覧ください)